※過去記事を直したいので、このブログは、しばらく2週間に1回の記事更新になります。よろしくお願いします。
これ書いている人は、長編小説の下読み年数のほうが長いですが、短編の応募の下読みに呼ばれたことがあります。
その時の経験から、
こういうことに気をつけて応募したほうがいいかも?
という、いくつかの項目を書いてみました。
※下読みは人なので個体差が結構あります。ここに書いてあることは、あくまでいち下読みの主観です。
規定違反
規定違反は即落とす、という賞もあるので、本当に気をつけて欲しいです。
サメダがよく見たのは、この辺の違反です。
特に指定のお題がある場合、それが入っていないと、賞によっては、話としてはよくできていても、落とさざるをえない時もあります。
そうなるとすごく、下読みとしては、めぐりあわせを恨みます。
「お題ナシの賞に応募してきてくれさえすれば……」みたいな気持ちになります。(下読みが通したからと言って、上が受賞させるとも限らないのですが)
「なんで私の作品、受賞作よりうまいのに落ちたの? 選考者クソ。」
と思う人は、お題をちゃんと使えていたかどうか? を、ぜひ振り返ってみてください。
使っているにしても、お題の使い方が凡庸だった、というケースも結構あります。
お題アリ公募だと、内容・技術いかんよりも、お題を深く射ぬいているかが、かなり重要視されがちな賞もあるなあという印象です。
話の途中で終わっている
どう考えてもまだ続くところで文章が切れている応募作、というのがときどきあります。
作者の意図で、そこで切ってあるのかもしれないですよね。
しかし、「これはもしかすると応募時にコピペに失敗したのかもしれない」と思うような唐突な切られ方の応募作もあります。
その場合、応募されてきた部分までで評価することになるので、通過は厳しくなりやすいです。
ちゃんと最後までコピペされているか、応募時によく確認するのは、大事です。

終わり部分に、「了」・「完」などのエンドマークをつけておくと、最後までコピペできたか確認しやすいかと思います。
ネタ被り
お題ありの場合、応募作同士で、ネタ被りが発生していることは、かなりあります。
なので、少なくとも、私はネタ被りを感じたくらいでは選考に影響させません。(このへん、下読みによる個体差があると思いますが……)
ただ、例えば「赤」というお題に対して、リンゴ・血・夕日など、そういう誰もが思いつくネタで応募した場合、同じネタの作品とまず比べられてしまいやすく、血で血を洗うクオリティ勝負に持ち込まれがちです。
それに、「斬新さ」という面で考えると、誰も思いついていないネタのほうが、下読みの記憶には残りやすいかなと思います(いち下読みの主観)。
抽象的なお題の場合、それをどう解釈し、作品に絡めるかの時点で、かなり勝敗が決まってきやすいので、よく吟味してから制作にかかったほうが、結果的に無駄がない気がします。
主人公に自分を重ねすぎている
実体験をネタにすると、小説にオリジナリティが出やすい反面、作者の存在が前に出すぎてしまうという問題があります。
それが行き過ぎると、小説というよりは、実体験エッセイになってしまうので、その塩梅には気をつけたいところです。
また、自分の願望・理想の展開を主人公に入れすぎてしまうと、主人公と作者の境界があいまいになり、夢小説的になりがちです。
応募前に第三者に観てもらい、客観性を保つのがベターかと思います。
なお、自分の政治的、宗教的信条を入れすぎるのもあまりおすすめできません。
例えば、現存する特定の国家や政治団体がいかに嫌いであろうと、そういうのを名前も変えずにダイレクトに(あるいは伏せていても伏せきれていないような解像度で)入れて、攻撃的に書くのは本当によくないです。
公募で勝ち上がるのに、おそらく妨げになるので今すぐやめたほうがいいです。
スピリチュアル系もデリケートなので、使う時は、言い回しや調理法をよく考えたほうがよいかと思います。
使いようによっては作品世界に深みが出るかと思うのですが、自分の見えている世界と、他人の見えている世界はけっこう違います。
自分の主観を世間一般の常識だと思い込みすぎず、これは読者に伝わる文章だろうか? という疑問を常に持ってみてください。
オチが弱い・まとまっていない
おそらく小説を書き慣れている作者なのだろうなと感じる、とても面白い応募作も多いです。
これは上の選考に上げるべきだ、と応援しながら読んでいると、しかし、オチが上手くまとまっておらず、結果的に強く推せなくなってしまう作品もありました。
上手くまとまっていないというのは、かならずしも破綻しているだけを意味しません。
破綻した作品は、そもそも終盤までの間に、既に違和感があることが多いです。
しかし、オチに至るまでの間「面白い」と読者に思わせられるようなレベルの作品だと、破綻オチであることは、あまりないです。
ここでいうオチが上手くまとまっていないというのは、荒っぽく言うと、「オチの納得感や読者の心にもたらす読後感が弱い」ことです。

そつのないオチになってしまっていることにより、記憶に残りにくく、その点で競争力が弱くなってしまいがちなのかなと個人的には感じました。
要は、真面目な感動オチに持っていけばいいんでしょ?
という見解は、半分あっていて半分違う気がします。
いわゆる泣ける感じに仕上げればいい、ということではなくて(なぜなら感動パターンのオチは多く、そうなるといかに泣けるか描写・展開のバトルになりがちだからです)、後味は悪くてもいいんです。激しいどんでん返しや人死にがなくてもいいんです。
強く心を震えさせるラスト、読後長く考え込んでしまうような結末、そういう意味でのインパクトがあると、大量の応募作の中から、抜きんでてきやすいのかなと感じました。
善悪が単純すぎる
短編なので、長編よりも人物の複雑みを出すのは難しいことだとは思います。
しかし、ある程度は善悪の構造を複雑にしておいた方が、物語としての読みごたえが増してよいかと思います。
あまり善悪が単純すぎると、道徳作文みたいになってしまう恐れがあるからです。
日常生活ではモラル高く生きていきたいものですが、ここは小説公募というバトルフィールドであり、そこでは物語性や没入感を求められるので、一般的に悪いとされるものやことを、「悪」として書くだけでは、物語として成立していきにくいです。
世の中には正義と悪で語れない、実にいろいろな社会問題がごろごろとあるので、そういうものからアイデアを得てみるのもいいかなと思います。(ただし安易にそのまま使うと当事者に失礼なので注意)
そういわれてもあんまり新聞とかも読まないしよくわからないなあ、という人は、たとえば、講師がかみ砕いて問題を教えてくれるので、カルチャーセンターに行ってみるのもいいかも。
・『実力も運のうち 能力主義は正義か? (ハヤカワ文庫NF) 』
圧倒的正論で論破してきがちな、界隈の成功者にイラっとした時に、この本を読むと気分が多少晴れる。ただちょっと内容は難しめ。
文章は平易なのですが、内容が難しめなので、個人的には紙の本で買ったほうがじっくり読みやすいかもという印象。(電子版もあります)
まとめ
とにかく、明日からできるお手軽公募ノウハウとしては、「規定は絶対に厳守」というただ一点です。そこで落ちると労力がもったいないです。
ところで、短編は応募数が多いので、落選者もその都度大量に出ます。落ちて選考者にムカついているのはあなただけではありません。
賞には運もありますし、相性もあります。あまり落ちたことについて考えすぎないことです。落選したてで冷静でいられないときは、落選について考えれば考えるほど腹が立つからです。
気分転換には旅行もいいのでかんがえてみて。
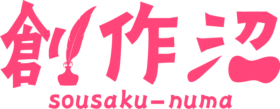
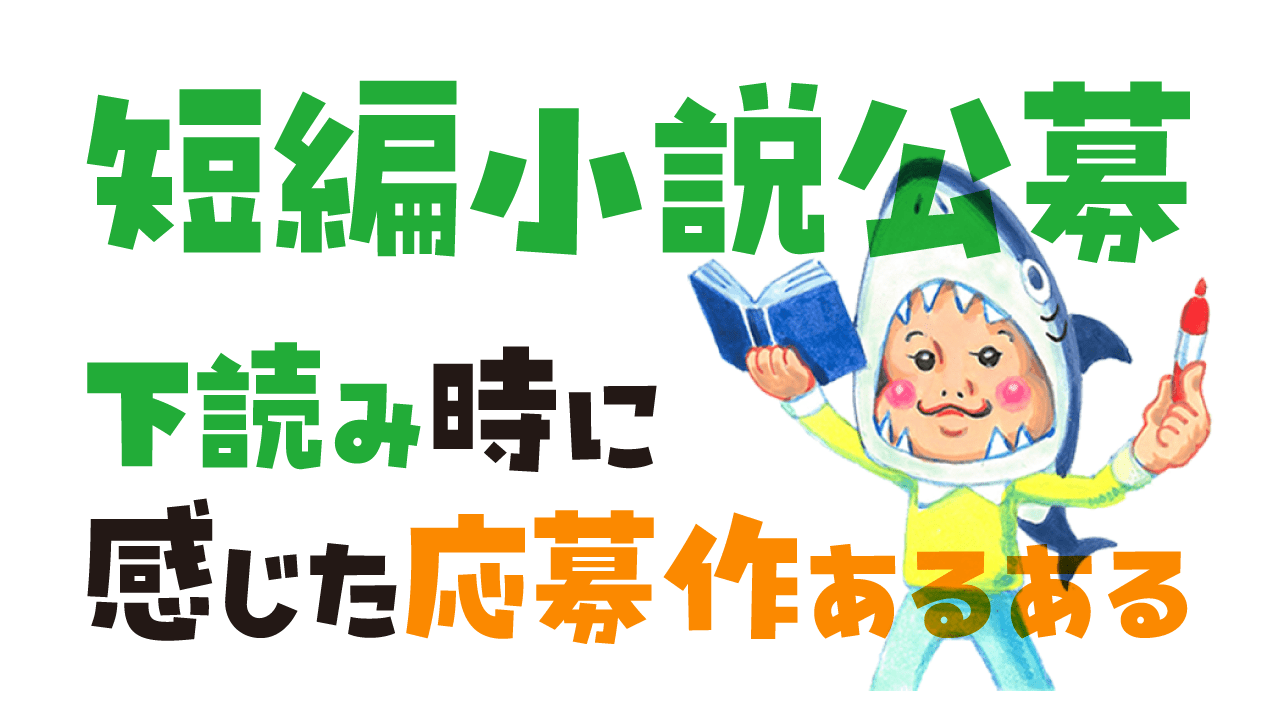

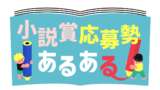

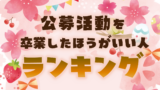
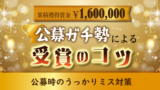
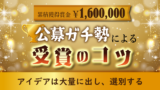
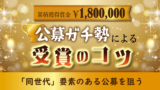
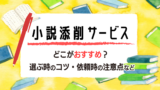


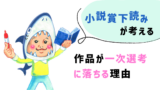

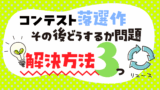

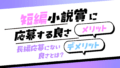
コメント