- カテゴリーエラーの作品って、送っても大丈夫なの?
- カテゴリーエラーをしないための方法が知りたい
こんにちは、わりと公募好きのサメダです。
イラスト系だと、100件くらいの受賞歴があります。
このシリーズ記事では、公募ガチ勢の末席を汚す著者が、こうしたら公募生活をいい感じに過ごせるんじゃないの、というコツみたいなものを書いています。
今回は、
カテエラ、つまり、カテゴリーエラーはOKなの、NGなの?
という点について書きます。
結論から言うと、基本的にNGです。
どういうことなのか、以下詳しく見ていきます。
カテゴリーエラーとは何か
カテエラとも呼ばれます。
特に文芸系賞の公募で使われている言葉なのですが、具体的にどういうことかと言うと、
本格歴史ものを募集している賞へ、転生チート主人公の小説を送りつけるようなことを言います。
いやそんな空気の読めないことはさすがにしないよ。
という人でも、例えば、溺愛ドロドロ物を求める賞で、恋愛薄め作品を送ることくらいはあるんじゃないでしょうか。
それもカテエラといえばカテエラです。
これ書いている人は小説賞の下読みなどもするのですが、お題や求められているジャンルとの乖離がひどい場合、かなり低次の選考で弾くことに決まっているケースもあります。
でもそうは言っても、

これまで見たことない作品を求む。とか、斬新な作品が見たい。みたいなことが、募集要項のところに書いてある賞もあるじゃない?
という声もあるかと思います。
それ、結果発表ページに行ってみて確認して欲しいんですが、案外、要素は目新しいけれど、基本的な部分はオーソドックスな内容、というの作品が受賞してませんか?
下読み時に、上が、だいたいこういう方向性の作品が欲しい、と条件を提示する場合もあります。
そういう場合は、その条件を満たしていてクオリティの高い作品から取っていくことになります。
この、「こういう方向性のものが欲しい」の、「こういう」という部分には、
- その賞では絶対に外せない要素を取りこぼしていないもの(青春ものの賞なら青春要素がちゃんと入っている作品、など)
- 売れそう(あるいは売り出したい)とそのレーベルが考えている要素
などが入ります。(賞によってまちまちです)
webで見た、ほかの下読み経験者の中には、〇〇というジャンルがウケているから、〇〇の入った話を上げてくれと言われた、という人もいるみたいです。
出版業界はかつてほどの体力がなくなってきていることもあるのか、「レベルは高いが売れ筋でない作品」や「面白いが尖り方がきつい」まで掬い上げてくれる機会は減っている印象です。
したがって、これ書いている人としては、「カテエラで応募しないほうが無難」という結論です。
カテエラ作品で応募するのは落選リスクが高い。かけた労力の無駄が大くなるので、基本的にカテエラ作品では応募しないほうがベター
尖り気味の文学で勝負したい人は、個人や小規模出版社主催の文学賞を検討してみては。
探せば、そういうものも受け入れてくれやすい傾向のところもあります。中には、受賞すると本や冊子にしてイベントで販売してくれるところもあります。
過去作を研究してカテゴリーエラーを回避
小説などの文芸系の場合
- 過去の受賞作を読む
- その出版社のそのレーベルが、過去にどんな作品を出しているかをよく研究する
これが、いわゆるその賞にとっての「場違い」な作品を、送らずに済むコツかなと思います。
そんな当たり前のことは知ってます。記事つまんないです。つまんないですけど、私の作品をタダで読んで感想ください。
という、メールがガチで来たことがあるのですが、すぐに上達・受賞できるようなアドバイスなどありはしない、と思っておいた方が真理に近い気がします。
また、締め切りに追われる公募勢が多いので、過去作の把握を実践できている人は、案外少ないのではないかと思います。
ライバルと差をつけたいと思う、本命の公募の場合は、やはり過去作研究もした方がいいです。
研究を自分で行うのがだるいと思う人は、ある程度お金を出して、有識者に傾向などを聞くという手もあります。
ただ、聞いてその通りにしたからってデビューが確約されるわけでもないし、有識者も、その賞からデビューしたか選考委員をやってるかでなければ、ある程度推測で発言している、ということは考慮に入れておいた方がいいです。
この企業の株価上がるんですか? とアナリストに聞くのに似ています。確率は高くなるけど保証はない、みたいな感じです。
送り先の賞の受賞作を全部読め、とは言いません。
でも、就職面接時に、全く業界研究せずに臨んだら、結果はなかなか出にくいですよね。公募も似たようなものです。
そのレーベルの受賞作で特に売れている本を、2、3冊読むだけでも違うと思います。
できれば読破するに越したことはないのですが、読書メーターやブクログなどの書評サイトで、ストーリーの概要を掴むだけでも、やらないよりましです。
ちょうど書き上げた作品があるから、適当な賞に送った。賞が取れた、という天才もいます。いますが、それはまれです。
書き始める前から特定の賞に応募すること想定して研究し、その賞向けに執筆するほうが、よりその賞を勝ち上がりやすい小説が書けるのではないかと思います。
自分でカテゴリーエラーかどうかわからない時は
友人知人・または第三者に読んでもらって客観的な意見をもらうのがよいか思います。
第三者とは誰なのかというと、個人的なおすすめは、作家、下読み、編集などの経験者です。
いなければ、応募したいジャンルの読書量の多い人に頼むのもいいかと思います。
- 添削サービスや添削講座に申し込む
- フィードバックをくれる賞に送る
執筆を周囲に秘密にしている人の場合は、スキマやココナラといったスキル販売サイトで、読書感想を書くサービスをやっている人がたくさんいるので、そういうサービスを使ってみるのも一考。
無料で済ませたいのであれば、X(旧・Twitter)で、小説読みます、RTした人の小説を読みに行く、などの#タグで検索すると、読んでくれる親切な方もいます。
ただ、無料ということは、頼んだ人に、「早くやって」だとか、「たくさん読んで」などと、要求しにくいということでもあります。
確実性を求めたいなら、お金をある程度出すのも検討してみては。
イラスト系の場合
例えば、(一般的な)年賀状公募に、アニメタッチの人物イラストを送るとほぼ確実にボツります。
それも一種のカテゴリーエラーだからです。
需要が少ないんです。
売れにくいから、採用されない。
一口にイラストといっても、web小説の挿絵に使うのか、児童書に使うのか、ビジネス系サイトに使うのかで、消費者層が違います。
ですので、過去の受賞作をよく見て、それと同じ雰囲気に寄せていくのが受賞の近道です。
あ、このイラスト公募は、アニメ風の透明感のあるイラストが多く採用されているな、とか、ここは主線のないコミカルな絵柄が毎年上位賞に入っているな、などとわかってくれば、攻略法を得たようなものです。
また、そのイラストを使う人の立場になって考えることも重要です。
そのイラストを用いた商品を使用する年代はどのくらいなのか。性別は。職業は?
など点についても考えてみるといいかも。ターゲット層のニーズや流行にアプローチするカラーリングや要素を入れると公募に勝ちやすいです。
ターゲット層について考えることは、イラストや文章制作を仕事として受けるときにも役立ちます。磨いておいて損はないスキルです。
まとめ
- カテゴリーエラーは基本的にNG。
- 公募する賞の研究をすれば、カテゴリーエラーはある程度、防げる。
このシリーズの次回記事では、嫉妬心コントロールについて書いています。

公募をしていると、嫉妬は日常ですよね。どうやって付き合うかについて考えてみました
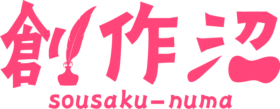


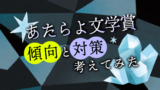


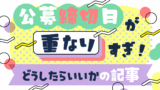
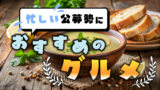

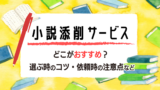
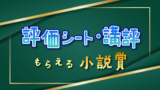
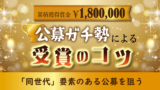
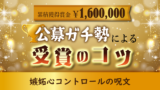
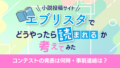

コメント