雑誌や書籍など、紙媒体のイラストお仕事をすると、出版された後に、刷り上がった現物(見本)を送付していただける場合が多いです。
自分の仕事が掲載されるのは嬉しいものですよね。宝物になるかと思います。
でも、喜ぶだけで終わってしまうのでは、次に繋がりにくいかもしれません。
では、見本誌をいただいたあと何をしたらいいのか?
という点について以下、具体的に書いていきます。あくまで一例です。

見本誌をいただいたら迅速にお礼
先方は、あなたに、お仕事をくれた上、忙しい中、見本誌まで送付してくれたのですから、ありがたいことですよね。
見本誌が届いたらまずお礼を伝えましょう。
届いたその日か、翌日くらいまでにはお礼のメッセージを送るとよいかと思います。
お礼が遅くなりすぎると、何についてのお礼かわからなくなりますし、こちらも先方も今更感が出てしまいます。
それに、何事もそうなのですが、送り先の人が「受け取った」と言ってこないと、送ったほうは、「ちゃんと届いてるのかな?」と不安になってしまうものです。
お礼は、無事、品物が届いていることの報告でもあります。
なお、お礼メッセージを送る時には、その見本誌の感想なども添えると印象に残りやすいかもしれません。
ただしネガティブなことを書くのは絶対NGです。
相手がもらって嬉しい感想を考えて書きましょう。
ところで、感想は、意外と読んでくださっている感じがします。
著者の体験になりますが、次号からの構成にさりげなく反映されていたり、感想をHPに掲載されたりしたこともあります。文章を書くのが好きな人は、腕の振るいどころかもしれません。
なお、語彙力が高まると表現の幅が広がります。小説書き向けですが、こういう本もあります↓
・『プロの小説家が教える クリエイターのための語彙力図鑑』
語彙力の本はほかにもたくさん出ているので、パラパラ見てみて、自分に合いそうなものを探すのがおすすめです。ネット販売でもサンプル画像が見られるところがもあるので、買う前に立ち読みしてみましょう。
もし、分厚い本などで、読むのに時間がかかりそうな場合も、送っていただいたことへの、お礼のメッセージだけは早めに送ったほうがよいかと思います。
その場合、いただいた本はゆっくり拝読させていただいておりますが、取り急ぎお礼まで、などというように伝えるのもひとつの手かと思います。
お礼はメールでOK
昔は電話や手紙でお礼をしたそうなのですが、今はメールでも失礼に当たらないと思います。
メールはいつでも見られるので、相手の時間を拘束しにくいところが、負担になりにくく親切かと思います。
メールは簡単に送れます。
しかし奥が深いので、メールひとつでお仕事がいただけたり、いただけなかったりと、明暗が分かれることもあります。
余力があったらビジネス的モテメールを研究するのもおすすめです。
・メールスキルUPのための本の例
『イラッとされないビジネスメール 正解 不正解』
営業は好感度が大事なので、イラっとされないポイントを押さえるのは大事かなと思います。
メール末尾には、またお仕事の機会があった場合、お声掛けいただけるよう、一言添えておくと、次回へのビジネスチャンスに繋がっていきやすいかもしれません。
もし習慣のある人は、年賀状を送るのも一考です。
その年、取引のあった企業に、年末、あらためて年賀状をお送りして過去の仕事のお礼を添えることで、思い出してもらえ、新たなご縁に繋がるかもしれません。
年賀状営業は、効果があるという人とないという人で、意見が分かれるみたいです。
ただ、1件100円以下で自分のイラスト入りはがきで営業をかけられると思えば、個人的には、余力があればチャレンジしてみてもいいのかな? と思います。著者は、年賀状営業でお仕事取れたことがあります。
SNSにUPする場合許可を取る
SNSで、お仕事報告をする人も多い昨今ですが、ちょっと注意する点があります。
- SNSで紹介する場合、タイトルは略さず正確に記載
- 本の表紙も中身も著作権があるので、UP時先方への確認推奨
特に、この2つです。
まず、お仕事報告の時、お仕事させていただいた掲載誌の名前を、絶対間違えないように注意しましょう。
タイトル名を間違えてSNSで発信してしまうと、求めている人に伝わりにくいですし、先方に失礼に当たります。
タイトルは直接打ち込むのではなくて、公式サイトでコピペするなどして、正確に記載して紹介することが大切です。
タイトルを略して書くのも、正式な紹介の場合、控えたほうがいいです。
次に、本の表紙や中身のデザインには著作権があります。自分のイラストが掲載されているからと言って、そのままページを写真に取ってSNSにUPすると、トラブルになる場合があります。
本の表紙のSNSへのUPは黙認される場合が多いのですが、念のため、先方の許可はとったほうがよいかと思います。
本文も、例えば、イラスト部分のみ公開可で、ほかの部分はぼかしを入れるように、ですとか、掲載紙によって独自の指示があると思います。
どういう体裁ならSNSに上げて紹介してよいかを、あらかじめ先方に確認し、その方法を遵守してSNSにUPしましょう。
また公開可能日などについても、フライングにならないように注意が必要です。先方との齟齬がないように、よくチェックしておきましょう。
納品した作品は、自分のものではあっても(著作権譲渡しない場合)、既に自分だけのものではありません。納品先に迷惑がかからないように配慮することが大切です。
・SNS(X)のフォロワーの増やし方についての記事はこちら↓
まとめ
お礼は迅速に。クライアントワークは、お客さんがあってこそです。信用を失わないように心がけましょう。
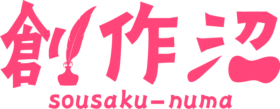


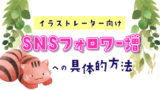

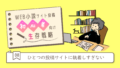

コメント