少し前から『国語便覧』が創作勢をはじめさまざまな界隈で話題になり、一時売り切れになる事象が起きました。
これ書いている人は学校で『国語便覧』を使わなかったので、どういうものか知らなかったのですが、そこまで話題になる理由を知りたかったので、実際買って読んでみました。
その上で、この本が創作勢にどう役に立つか、おすすめページなどを書いてみました。
※なお、これ書いている人の買った『国語便覧』は、数研出版のものであり、この記事の内容も、それに準じています。
『国語便覧』とは?
国語に関するさまざまな資料を掲載した資料集。
副教材として使う学校もあるみたいです。
『国語便覧』と名の付く本は、数研出版、第一学習社、浜島書店など、複数の出版社から出ています。
数研出版の国語便覧の内容
数研出版の国語便覧は、およそ520ページで、5章立てです。
以下のような構成になっています。
- 古文編
- 現代文編
- 漢文編
- 表現編
- 資料編
古文編に一番多くページ数が割かれており、本全体のうちの3分の2以上のボリュームです。
百人一首は百種全部が、現代語訳とそれを読み解くための背景解説がセットの状態で掲載。
源氏物語については16ページにわたって解説がなされるという手厚さ。
各回のダイジェストや、その回で源氏が何歳だったかなどの情報もついており、親切さがすごいです。
読んでみた印象
『国語便覧』(数研出版)は、載っている情報が膨大です。
ですので、(人によると思いますが)、小説のように1ページ目から真面目に読んでいくと、おそらく途中で挫折する可能性が高いです。
どっちかというと、辞書的な使い方が、向いている印象です。
これは個人的なおすすめ読み方なのですが、まずは、ぱらぱらとめくってみて、まずは興味ある時代や文学、作家のページから見はじめる。
次に、それに関係している別のページも徐々に見ていく。
というような読み方だと、挫折せずに、気楽に長く楽しめそうな気がしました。
この本の情報のまとめ方が、理解しやすいものかは人によると思うのですが、詰め込まれている情報量(カラー多めで520ページくらいある)に対して、お得感のある価格設定だと思います。
数研出版の国語便覧読んでみた創作勢によるおすすめポイント
言葉の引き出しが増える
文章系創作(特に公募)において、「日本語がおかしい」というワードは良く飛び交いがちですが、あなたはそういうとき、日本語がどうおかしいのか、的確に言語化できるでしょうか。
この国語便覧には、「遠い昔に学校で習ったような気がするけど、あってるかどうか、いまさら人に聞きにくいな……」という文章の基本が載っているページがあります。個人的にはそういうページがありがたいと感じました。
個人的におすすめなページ
・p430からの表現編
小説を書く以前の、文章の基本的なところを説明してくれています。
文章を書くときに、ここは気をつけたほうがいいよ、というような内容が載っています。
たとえば、一文を長くしすぎない、ですとか、意味の切れ目で読点を打つ、主語と述語を対応させる、原稿用紙の使い方、などの内容です。
個人的になんとなくうれしかったのは、読書感想文の書き方ページと、修辞法が載っているページです。
読書感想文のノウハウは、web小説界隈で活動している人は、友達の作品について感想を書くことも多いと思うので、役に立つかもしれないです(この指示通りに書くとちょっと真面目なものが仕上がる気がしますけど、ヒントにはなりそうです)。
絵描き勢にも役に立つ
日本の歴史については、写真がかなり多いです。(中国も多少もある。西洋は少ない)
『○○の描き方事典』みたいなイラストノウハウ本が、実用的でいいのはたしかです。
ですが、日本の歴史について軽く要所を押さえながら、衣食住をカラーで見られ、約1,000円程度で購入できると思うと、『国語便覧』もかなりアツい本だと言えます。
個人的におすすめなページ
・p49くらいまでの平安の衣食住の再現カラー写真
作画用の本ではないので、これを見ただけではおそらく細密には描写できないんですけども、牛車のこの部分の名前何ていうの? ですとか、この楽器は何ていう名前でサイズはどのくらいでいつ使うの? などのことが、ビジュアルと同時に知ることができる点が魅力です。
そもそもわからないものを描くとき時って、何を押さえたらいいのかわからないものなので、基本的なことがだいぶわかるというよさがあります。
創作のネタがいっぱい落ちている
この本は、とにかく情報量が多いので、どのページを開いても、ネタに事欠きません。
創作のインスピレーションは、インプットしないことには湧きにくいので、その点で情報量の多い『国語便覧』は、よさがあるかなと思います。
※もちろん、『国語便覧』は国語学習者向け本であり、創作ネタ専用の本ではないので、『国語便覧』で拾ったネタを各自別の資料によって深掘り・肉付けしていく必要はあります。
個人的におすすめなページ
・p64:平安の官位がまとめられているページ
そもそもこの国語便覧じたいが、かなり写真モリモリで、特に平安時代に手厚い印象です。
官位表まで載っているのがすごい……。
こういうのを載せてあると、「違うそうじゃない」と叫ぶ人が必ず出てくるので、たぶんこの表も、おそらく時代によって異同があるとは思います。ただ、参考文献も書いてあるので、気になる人は、そちらでさらに深掘りできるかも……?
・p210:日本の物価の変遷表(明治20年から令和2年まで)
ラーメン、あんぱん、コーヒー、週刊誌、新聞購読料、プロ野球観覧料、映画入場料などの値段の推移が、表になっています。
時代の相場感を知っておけば、創作のリアリティが増すかも。
・p220:文芸雑誌一覧
文フリなどで自分で文芸誌をつくりたい。
でも「っぽい表紙ってどんなものかな……?」とアイデアが浮かばない人に向いているページ。
過去に日本で発行された文芸誌の表紙が写真で載っており、レトロな文芸雑誌の表紙作りたい人は参考になりそう。
現代っぽいスタイリッシュな表紙を作りたい、という人は普通に現在発行されている文芸誌の表紙を、リアル書店かweb書店で見てきた方がいいかとは思います。
・P242~:著名作家の代表作と作家の背景
創作には、物語の舞台や登場人物の背景をリアルに描く力が求められると思うのですが、このページは、その時代に生きたクリエイターが、どのような暮らしをして、どういう考えのもとに作品を書いたかが、かなり詳しく載っているので、読み物として面白いです。
「有名な小説らしいし聞いたことはあるけど読んだことない。でも今更読むのもだるい」
という人にも向いている気がします。
ダイジェストで内容を説明してくれている作品もたくさんあり、興味が湧いたら実際読んでみるという流れに進みやすい作りです。
まとめ
『国語便覧』は情報量に対して値段が廉価で、コスパ的にお得感があります。
読みやすい構成なのかどうかは賛否が分かれるところかと思いますが、創作の「土台」を築くための資料集としての機能が高い印象です。
なお、似たような系統のコスパ良の、学生向け学習資料集にはこういうものもあります↓
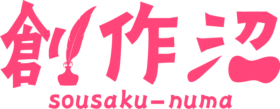
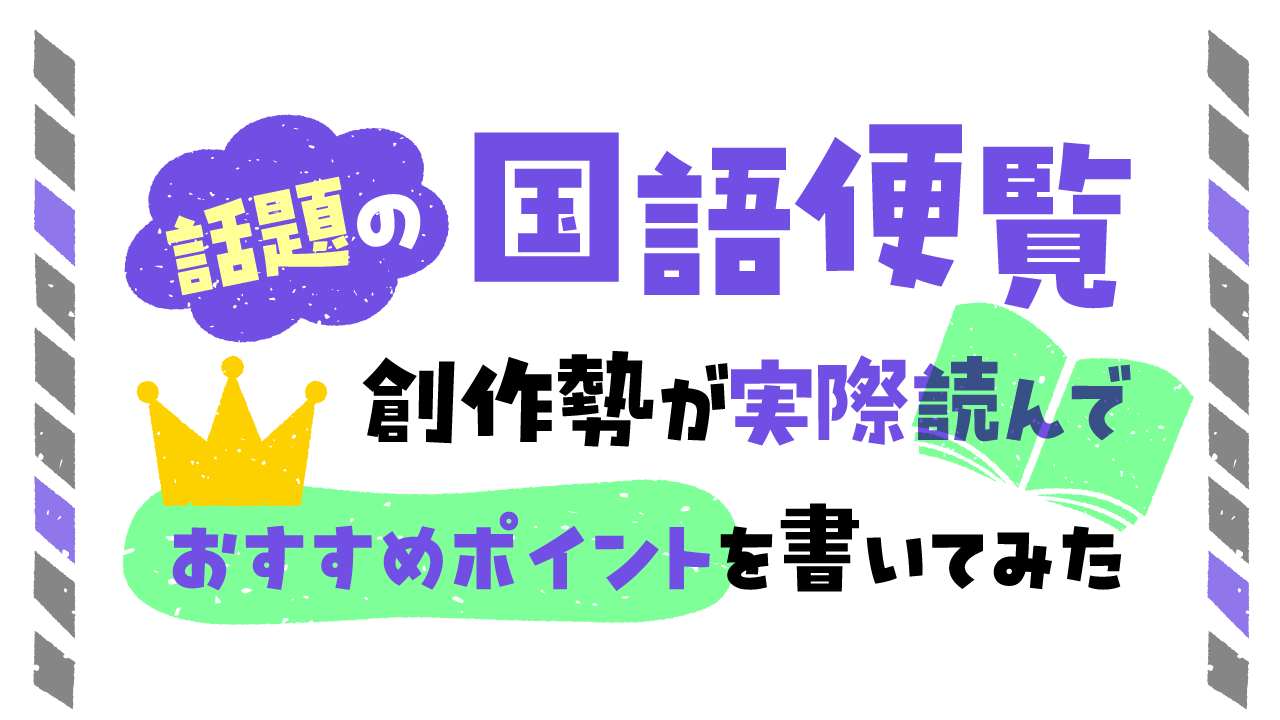


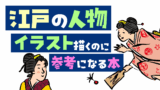

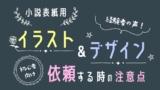
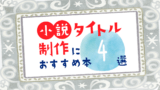
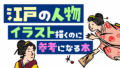
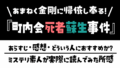
コメント