自分の小説作品を発表してみたい。
webで発表しているだけではちょっと物足りない。

本になるといいのに……
そう思っても、公募で受賞して本になるのはごく一握りですよね。
でも、本を作るのは出版社じゃないとダメ、なんてことはありません。
文学フリマなどのイベントや、通販などで、自分で作った本を頒布することもできます。複数の人の作品を一冊にまとめたものは、アンソロジーと呼ばれたりします。
そして、作品発表の場としては、そのアンソロジーに寄稿させてもらうという手があります。
以下そのメリットデメリット、注意点等について、書いていきたいと思います。
寄稿者になる時に心がけたいこと
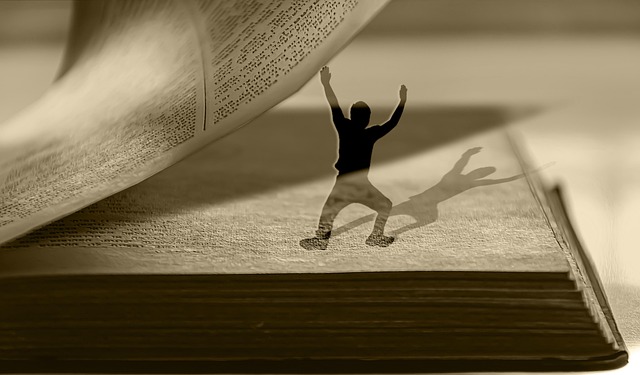
- 作品提出期限を守る
- 作品制作要項をよく読んで守る
- 連絡・返信はなるべく早めに
- 周囲と表立って揉めない
アンソロジー寄稿は、他人様の出している本の一部を間借りするケースが多いので、他の寄稿メンバーと主催者に失礼のないようにするのが、すごく大事です。
特に、締め切りは絶対に守るよう執筆スケジュールを管理していきましょう。
この人を呼んでよかった、と思わせる作品が寄稿できるとなおベター。しかし一番大事なのは〆切を守ることです!
個人主催の小説アンソロでよくある傾向
- 掲載スペースが限られているので、掌編・短編を求められることが多い
- だいたい何かテーマが決まっており、そのテーマに沿って書く
- イベント合わせで作られる
お題アリの短編を、他人と被らないようなネタで書ける人ほど、アンソロジーの寄稿に向いているかと思います。
また、イベント合わせで作られることが多いので、〆切を守れる人が信頼されます。
小説アンソロジーに参加するメリットデメリット
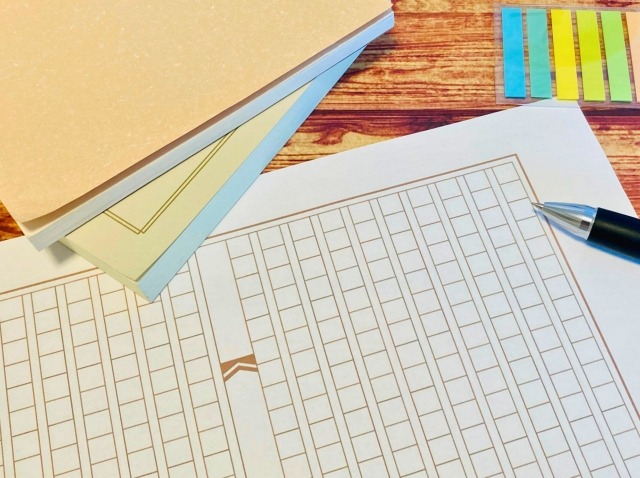
メリット
アンソロジーのいいところは、自分の普段の宣伝では届いていなかった層にも作品が届く可能性があるということです。
他の寄稿者の作品目当ての読み手が、そのついでに、あなたの作品に触れてくれるかもしれないところが魅力です。
また、同じアンソロに寄稿した書き手どうしは、一体感を感じやすく、交流が始まりやすいです。
交流しだすと「この人すこぶる気が合わんな」と感じ疎遠になる場合もあるのですが、逆に、寄稿後も長く交流が続くような、波長の合う人と知り合うこともあります。
これまで知らなかった書き手の作品に触れると、刺激が大きく、自分の引き出しも増えていきやすいので、そういう点でもアンソロはおススメです。
また、アンソロジーは多く、イベントに合わせて作ったりするのですが、主催者は集まった作品をレイアウトして印刷所にデータを送り、印刷代金を払い、本にしたあと、交通費を払い、イベント会場のスペース代を払い、時間を割いて、頒布してくださいます。
自分でできない人にとっては、すごくありがたいですよね……
デメリット
個人主催の場合、開催者のアンソロジー制作・販売に関わる作業は膨大で、負担がとても大きいです。予算も少ないことが多いです。
そのため、寄稿者への謝礼は薄いです。
刷り上がった本を1冊貰える、くらいだと思っておくのが無難。(※あなたが有名人で、かつ依頼されて書く場合は、アンソロによっては、いくらか謝礼をもらえる場合もあるようです)
アンソロジーへの参加ルート
例えばこのようなルートがあります。
- 自分で主催する
- 知人に誘われる・紹介してもらう
- 知人以外の方が開催しているアンソロジー公募告知に応募
自分で主催する
自分で主催すれば、表紙絵・テーマ・寄稿者に至るまで、(お金と相手のスケジュールが許す限り)かなり自分の好きな感じにできると思います。
デザインやをも好きな人は、自分で本を作る楽しさが強く味わえるかと思います。
ただ、上にも書いた通り、アンソロジーを編む作業は、かなりの時間的・経済的な負担があります。
アンソロ主催になったことで、人間関係や寄稿者が起こすトラブルで疲れてしまったりする人もいるようです。
ですので、経験のない状態でアンソロを立ち上げるのは少し不安です。
ビギナーは、まずはどこかのアンソロジーに参加させてもらい、十分アンソロジー制作の流れを掴んでから、主催に取り組んでみては。
知人に誘われる・紹介してもらう
あなたの親しくしている人に、本を作り、頒布した経験のある一次創作勢はいないでしょうか。
その人にアンソロジーの刊行経験があれば、チャンスです。
「機会があれば、次回は参加してみたい」という旨を伝えてみましょう。
ただ、アンソロ参加について、しつこく要求するのはNGです。その相手にだって、小説の好みがあります。あなたの作風は、好みでないかもしれません。
チャンスの種まきをする意味合いで、アンソロに参加したい、と普段から周囲に言っておくのもいいかも。
また、別の方法として、知人の知人がアンソロを企画している場合、その知人を介してアンソロに呼んでもらうという手があります。
ただ、こちらも脈がなさそうならすぐ引くくらいの感じで、強引になりすぎないようにしましょう。
もし、紹介によって運よく寄稿者に加えてもらった場合、言動にはよく気をつけてください。
紹介でアンソロに呼んでもらった場合、問題を起こすと、自分だけでなく、紹介者の立場まで悪くしてしまうからです。
あとでギクシャクしないためにも、紹介による寄稿時は、特に責任ある行動を心掛けるのがベター
知人以外の方が開催しているアンソロジー公募告知に応募
「すごく興味のあるテーマのアンソロ企画が立ち上がり、寄稿者を募集している、でも主催者はこれまで全くかかわりのなかった人だ」ということもあるかもしれません。
そういう時は、まず要項をよく読んで、条件を満たしてから、規定の方法で参加申し込みをしましょう。
全然知らない人に連絡を取ることになるわけなので、初めが肝心です。
丁寧な文言を心掛けましょう。
これはあくまで例ですが、以下のようなことをファーストコンタクト時に添えておくと、相手もあなたの素性がわかりやすく、安心しやすいです。
とにかく、親しくない人に連絡するわけですので、まずはちゃんと適切な距離感を保ちます。
タメ口や上から目線は、身内なら許容されるかもしれないのですが、この場合は絶対にNGです。
相手は営業先の人だと考えてください。
アンソロジーの募集形態

例えばこういうケースがあります
- 参加者を募る
- 作品を募る
どちらの募集形態にも、参加者にとってメリットデメリットがあります。
参加者を募るケースでは、作品が出来上がっていなくても参加を表明できるのが気軽でメリットですが、参加表明後、締め切りまでに書けないと信頼を失います。
一方、作品で採否を選ぶ場合は、「アンソロジーの入稿時期が迫っているのに作品が書けずにパニックになる」という事態が起こらないのがメリット。
しかし、選抜で落ちると、作品を書いていた時間は無駄になるというデメリットがあります。
アンソロジー参加が歓迎されやすい人とは
アンソロジー参加が歓迎されやすい人は、例えば以下のような人です。
- 小説が上手い人
- 肩書が強い人
- SNSなどで人気があり、拡散力が強い人
アンソロジーを作ったら、ふつうはたくさん売りたいものですので、売れやすい本にしたいと考えることが多いです。
なるべく、「この人が載っているのなら買いたい」と多くの人が思うような、人気や肩書のある書き手を集めたいんですね。
プロ・書籍化作家・受賞経験者、賞の常連、SNSなどで人気や拡散力のある人などが上げられます。
ただ、プロになるのも書籍化するのも自分の力ではどうにもならない要素が多いですよね。
ですので、比較的努力でなんとかならないこともない、小規模賞の「受賞経験」などを積み上げておくのがコツです。
日ごろから、自分の創作物の価値を高めておきましょう。
ただ、アンソロジーに載りたい書き手はけっこう多いので、いくら肩書や賞歴があっても、ただ待っているだけで誘ってもらえると思わないほうが良いです。
特に、全然知らない方の人気の出そうなアンソロにぜひ参加したいと思う場合、受賞歴をつけた状態で、自分で売り込むくらいでないと、掲載枠を獲得することは難しいかも。
小説アンソロジーに参加するときのステップごとの注意点
アンソロジー企画の探し方
アンソロジーに寄稿するには、まず寄稿者を募集しているアンソロを探すところからです。
方法はいくつかあります。組み合わせて使うのがベターです。
個人的な印象では、Xでの告知を探すのが、見つけやすい気がします。
アンソロジー・アンソロ・寄稿者募集・小説募集・小説
のようなワードを組み合わせて探してみてください。
検索して探す場合に注意したいのは、ちゃんと一次創作で、小説の募集なのか? という点を確認することです。アンソロは二次創作でも行われる文化なので、行き違いが起こらないように気をつけてください。
また、文学フリマのwebカタログで、何回もアンソロジーを頒布してらっしゃる方を探してみるのもいいかもしれません。
そういう方は、新しいイベントに向けて、アンソロ企画を考えている可能性があります。
応募から採用まで
すごく基本的なことなのですが、そのアンソロ企画が、外部に開かれているものなのか、相手に声をかける前に、よく確認してください。
内輪だけで楽しみたいアンソロ主催者もいます。
必ず、応募したいと思ったアンソロが公募制を採っているか、参加資格を満たしているかを、要項を読んでじっくり確認してください。
内輪で楽しみたい人たちの間に無理に割り込んでもなにもいいことはありません。ノリと話題について行けない虚無感だけが残ります。
また公募制のアンソロジーの場合は、応募者数によっては、落選する人も出てきます。
個人のアンソロなので、作品の上手さよりも、主催者との関係性で採否が決まることもあるかもしれません。特に、主催者が金を出す場合、それは致し方ないことです。
そこに文句があるのならば、出版社の公募に投げたほうがいいです(それはそれで、出版社のカラーに合わなければ採用されない地獄があるのですが)
とにかく、アンソロに採用されなくてもSNSで荒ぶりすぎないように気をつけてください。
そもそも、落ちたらしばらくギクシャクしてしまうような関係性の人が主催するアンソロに、応募することは、控えておいた方がいいのかもしれません。
作品の納品まで
参加OKとなったら次に気をつけることは以下です。
このステップで一番大事なのは、必ず作品提出日と要項を守ることです。
主催者はおおむね、イベントの期日に向けて刊行のスケジュールを組んでいるので、誰か〆切を守らない人がいると、次の組版作業や校正などの作業が後ろ倒しになっていき、最悪、目標のイベントの日に本が出ない、ということになります。
そうなると主催者と他の参加者に、すごく恨まれます。
時間や連絡ごとにルーズな参加者は、主催者や他のメンバーにとって頭の痛い存在であり、次から執筆メンバーから外されても文句は言えないです。
遅れそうな時や、病気・トラブルなどで寄稿自体ができなくなった時は、早めに主催者に連絡しましょう。
遅れることを告げると、怒られるかな、とか気まずい、とか思うかもしれないのですが、〆切を破られたり突然音信不通になられるよりは、ずっと主催者的には助かります。わからないところも、早めに聞くのが◎
作品を提出した後
大事なのは刷り上がった本が頒布されるイベント日です。
そのイベント日になるべくたくさん集客できるよう、こまめに宣伝していきましょう。
見ている人はあんまり興味がなかったり、あってもけっこう忘れがちなので、いつも書影と一緒に宣伝するのが効果が高いかと思います。
とはいえあまりに宣伝しすぎると、アンソロに関係していないフォロワーは辟易するので、「イベントまで宣伝多めになりますので、うるさかったらリポストをオフにしてください」などと一言ことわっておくといいかもしれません。
また見本誌が手元に届いたら、読んで、本の感想をSNSで書くのがおすすめです。
そのアンソロが盛り上がっていきやすいです。
ちょっと大変ですが、寄稿者全員の作品感想を書くと、とても喜ばれやすいです。
アンソロ寄稿で〆切の次に気をつけること
炎上です。
アンソロへの参加を表明しているあなたが、SNSでトラブルを起こしたり問題発言で炎上したりすると、参加しているアンソロジーの寄稿者、主催者にもとばっちりが行く可能性があります。
炎上商法を狙っているのだ、などとポジティブに考えてはいけません。この場合、自分ひとりの問題ではないからです。
アンソロ発売前後は、特に言動には気をつけましょう。
誰かを誹謗中傷したり、荒ぶったりするのはとにかく避けてるのが大事。愚痴を吐くにしても、せめて見えないところでひっそりやりましょう。
まとめ
アンソロジーは、雑に言えば、他人様の出している本の一部を間借りすることなので、失礼のないようにするのと、この人を呼んでよかった、と思わせる作品作りを心掛けていくのが大事。
寄稿者と主催者は持ちつ持たれつなので、お互いの時間を奪い合わないように、〆切は厳守、連絡はこまめに、がベター。
作品宣伝は、アンソロの売れ行きを左右するので是非行いましょう。
アンソロの反応が良ければ次も企画が立ち上がるかもしれません。自分のためでもあります。
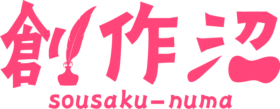
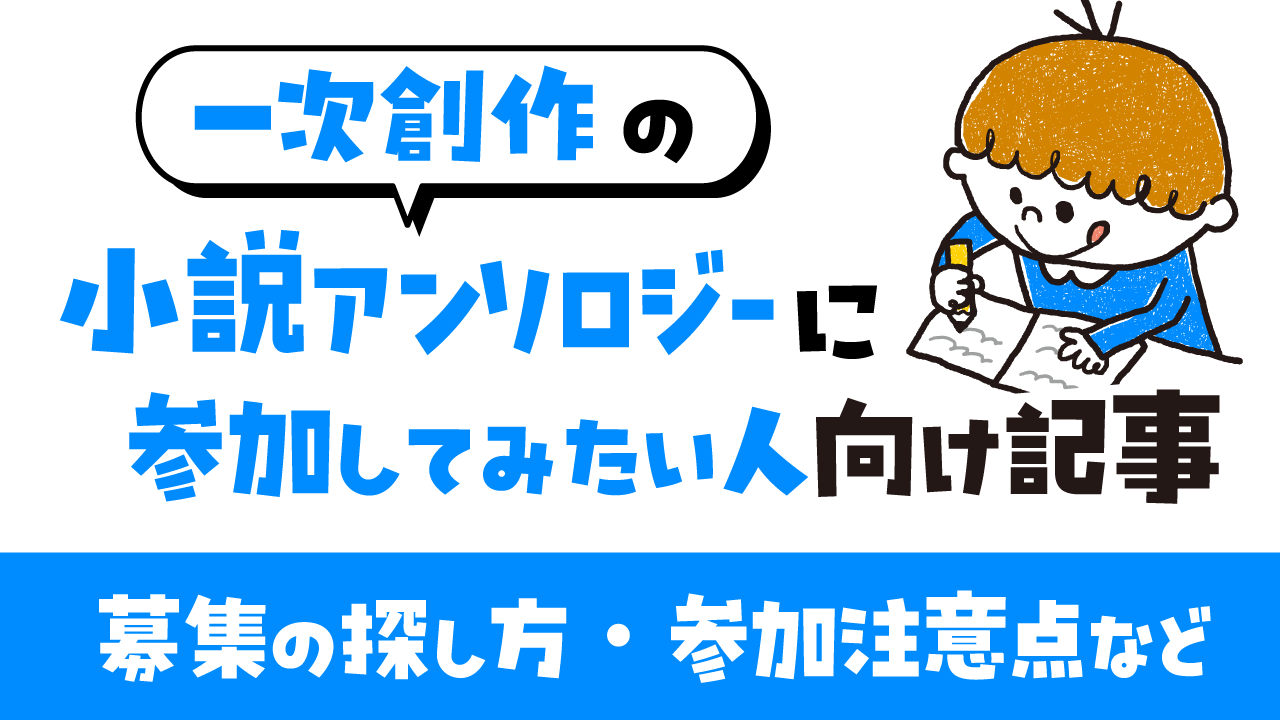

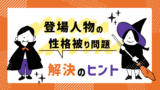

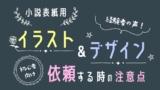
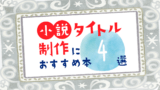
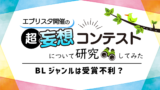
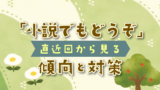
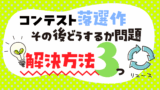
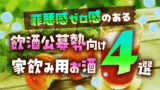
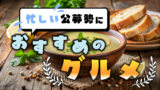



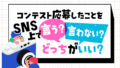
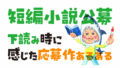
コメント