公募に応募した。落選した。
思い入れがあったり、気に入っている作品だと、受賞しなかったのも悲しいし、世に出ないということにも未練があるのではないでしょうか。
そういう激重感情を抱えた落選作をどう扱ったらいいのかについて、公募勢のサメダが考えてみた記事が以下です。
作品をどうしたいかをまず決める
まず自分が、その落選作をどう扱いたいか? を決めます。
- まだ公募あきらめていない人→選択肢Aへ
- 人に見せたい→選択肢Bへ
- 誰にも見せたくない→選択肢Cへ
選択肢A:他公募に使いまわす
まだ公募への心が折れてない、という人はこちらの選択肢がおすすめです。
- もしかすると運がよくて次は賞が取れるかもしれない
- 一次落ちした作品が別の賞で途中選考に通ると、復讐心みたいなものがある程度満たせる
- また落選のショックを味わうかもしれない
- 落選に心が耐えられないようならやめたほうがいい
別に一度落ちようが、規約に使いまわし作品禁止、と書かれていない限りにおいて、落選作を使いまわすことは自由です。
落選作品をほぼ改変せずに再応募して受賞したケースはけっこうあるようです。(小説についてはわかつきひかる先生の動画で例が出ていますので、興味がある人はそちらを見るといいかも)
カテエラによって落ちたのであれば、適切な公募に送りなおすことで、結果が期待できる可能性があります。
ただ、サメダは下読み経験者なのですが、やはり落ちるには落ちるだけの理由があると感じることも多いです。
その賞が要求している内容を的確に射抜く作品に仕上げなおして応募したほうがいいのは間違いないです。
選択肢B:発表する
webポートフォリオに掲載する
ポートフォリオは作品集のことです。
どういう形式のものがポートフォリオに当たるのか?
と悩む人もいるかと思うのですが、広義の解釈では、作品をいくつか集めて置いてあればそれは作品集と言ってもいいかと思います。
ですので、投稿サイトに作品を投稿するのも、いわゆる「ポートフォリオ」サイトに置いておくのも、見せ方次第でポートフォリオであることには違いないです。
閲覧者からの反応が欲しかったり、仕事へつなげたい場合は、プロフィール欄に連絡先を明記するのが重要です。
ただ、メールアドレスを直接書くといたずらにあうことも少なくない様子なので、作者への問い合わせフォームのあるページへのリンクを貼っておくのが無難かなと思います。
・Xfolio:HPを作る際、カスタマイズ機能を使うと問い合わせフォームを作れます。「お仕事」「作品への感想」など、ユーザーが何について問い合わせるのか、という選択肢欄も自作することができます。
・note:アカウントを持っていさえすれば、デフォルトで問い合わせ機能が実装されています。とても分かりにくいのですが、その人のアカウントを一番下までスクロールしていくと「クリエイターへのお問い合わせ」というのがあり、そこから問い合わせができます。なお、このフォームから一人が一日に送れるメッセージの件数は上限があるっぽい様子です。
- foriioも「仕事依頼」という形でならメッセージを送れます。
- pixivはアカウントを取ってログインすればメッセージを送れます。
無料ポートフォリオサイトとして利用できそうな投稿サービス例
小説とイラスト、どっちでも使えるという縛りで、個人的によさげだと思うところをいくつか挙げてみます。
- pixiv(ピクシブ)
- Xfolio(クロスフォリオ)
- foriio(フォリオ)
などがあります。
pixivとクロスフォリオは、いわゆるマンガ・アニメ・ゲーム・萌えなどの要素を含むエンタメ系の作風のお絵かき勢、文字書き勢が多いです。
またどちらも、投稿物に関しては、閲覧者が評価を入れることができるシステムです。
クロスフォリオは、イラスト、テキスト(長文)、どちらのポートフォリオにもしやすいです。
- イラストも描くし小説も書く、という人
- ホームページをある程度カスタマイズしたい人
- 自作品の販売もしたい人
- 閲覧制限を細かくかけたい創作勢
は、特に向いているんじゃないかなと思います。
閲覧制限に関しては、以下のような範囲での公開ができるようです
- 全公開
- ユーザーリストに入っている人のみ
- パスワードを知っている人のみ
- ファンコミュニティの支援者のみ(商品として販売時のみ使える)
- 非公開
ページごとに閲覧の制限範囲を変えられる点が魅力かなと思います。
また、AI対策をわりと気をつけてくれているサイトかなという印象です。
pixivもイラスト、テキスト(長文)どちらも対応していますが、どちらかというとイラスト向きです。
pixivは二次創作が強いのですが、比較的古くからあるサービスなので、作品投稿数も多いです。
つまり、なにかのついでにやってきた人が、見てくれやすいという点がいいかなと思います。
小説も投稿できるのですが、小説投稿サイトに比べると、投稿まわりのユーザビリティがあまりよくないと言わざるを得ないです。
ただ、二次の小説は、一般的な小説投稿サイトだと、投稿禁止のところや一部ジャンルのみがOKのところが多いです。
そのため、二次小説を書くなら、二次の強いpixivにアカウントを取っておいて損はないです。
- 二次もたしなむ一次創作勢
- 自作品を販売したい人
- 閲覧に制限をかけたい創作勢
上に当てはまる人はpixivが向いているかなという印象です。
公開範囲は以下が選べます
- 全体に公開
- ログインユーザーに公開
- マイピクに公開
- 非公開
また、BOOTHという創作物販売ができるサイトがあるのですが、そちらはpixivのアカウントで利用するので、pixivアカウントを取っておくと、自作品の販売までがスムーズに行いやすいかもしれません。
foriioはポートフォリオに特化したサービスみたいなので、上記2つのサイトとは違い、作品を投稿して閲覧者から評価をもらう機能はありません。
エンタメ系のクリエイターもいつつも、一般文芸編集者やライター、デザイナー、映像クリエイター、フォトグラファーなども使っている様子です。
foriioはイラスト等、ビジュアルの投稿に向いています。
また、webのあちこちに置いてある自創作をひとところに集めて表示させるのに向いています。(小説に関しては、サイトに小説自体を置くことはたぶんできないです。複数の小説投稿サイトに置いてある小説の作品リンク先を一覧で表示したい、という人に向いているのかなと思います)
なお、気の利いた文芸系ポートフォリオを作りたい考えている人には、こちらの雑誌で特集が組まれているので、それを参考にしてみるのもいいかもしれません↓
有料ポートフォリオサイト例
絶対にAI学習されないサイトというのはおそらくないので、そのリスクをどのくらい取っていくかは個人の考え方しだいかと思います。
イベントで配布・販売
落選作をちょっと凝った形にして発表したいなと思った人は、一次創作系イベントと相性がいいです。
- 実際に人と会えるので創作仲間との交流が広がりやすい
- 作品を実物として残して記念にできる
- 発行部数を見誤ると、在庫を大量に抱える可能性がある
- イベント参加は都度、お金がかかりがち
創作のイベントは例えば、
- コミティア(イラスト・マンガ描きにおすすめ・文字書きも多少いる)
- 文学フリマ(物書きにおすすめ)
- 各地の創作系イベント
- ジャンルを絞った創作系イベント(JUNE・BL系創作メインだと、J庭)
などがあります。
また作品を展示して仕事につなげようとする本気度の高いクリエイターには、ちょっと方向性がかなりガチなので軽い気持ちでおすすめはしにくいのすが、
クリエイターEXPOという展示会があります。
上記のコミティアや文フリ等の創作系イベントに比べると、桁違いの費用がかかります(ポートフォリオや掲示物の印刷代・宿泊日交通費等もろもろ込みで30万ほどかかるという人も)。ただ、出版社や企業の中の人もかなり来る展示会なので、即商談になった、という人もいるようです。
創作イベントは一種のお祭りであり、会場に行かないと味わえない特別の楽しさや熱があります。
デメリットは、参加にはわりとお金がかかりがちという点です。
例えば、出店(出展)側だとこのような出費が想定されます。
- 出店料(販売側として参加すると大体かかる)
- イベント会場までの往復交通費、食費、宿泊費
- イベントへの搬入搬出の送料(部数による)
- 作品の印刷代
- 作品の表紙デザインや組版を人に任せる場合その費用
- ブースに展示するための什器代
- アンソロを作る場合は寄稿料(誰に依頼するかによる)
ある程度、お金と時間に余裕ある人向けの趣味と言えるかもしれません。
ただ、イベント頒布物は、凝った作りにしようと思えば、金と労力とセンス次第で、どこまででも自分好みに追求できます。この点は魅力的で、自作品に愛着がある人は、楽しい趣味になりえます。
同人誌やZINEを安く作ろうと思えば、少部数から受け付けOKの同人誌対応の印刷会社が検索すればいろいろ見つかるので、それらを探してみるといいかと思います。
なお、文学フリマの東京開催回は近年かなり混雑している様子です(コミケ勢に言わせると大したことないという話ですが)。
また、プロ・企業のブースにお客さん吸われてしまいがち問題や商業主義傾倒はいかがなものか問題も、たびたび議論になっているようです。(とはいえ、大手・企業との格差問題は、創作イベント界隈では昔からよくあり、文フリ固有の事情というわけでもないかと思います)
事前告知に相当力を入れないと、無名のクリエイターは見てもらいにくい、厳しい状況になっているという部分はあるようです。
地方の文学フリマに参加してみて、ある程度イベント慣れしてから東京回に参加してみるのもいいかもしれません。
電子データとして配布・販売
イベントは混んでいるし、人と関わるのは苦手。でも自作品は売ってみたい。
という人に向いているのが、電子データでの配布・販売です。
この方法だと在庫を抱えなくていいし、初期投資がイベントでの販売よりずっと安く済むのも素敵なところです。
- 人嫌いでも創作物を売れる
- 一度販売データを登録すれば、放置しておいてもいい
- 在庫を抱えなくて済む
- 販売手数料が高め
電子データを販売配布できる場所の一例としては
- BOOTH(ブース)
- note(ノート)
- Xfolio(クロスフォリオ)
- BASE(ベイス)
- SUZURI(スズリ)
- kindle
などがあります。
販売手数料やアップロードできるデータ形式、アップロードしていい内容などが違うので、自分に一番合ったところを選んでみるといいかと思います。
どのサイトで販売する時でも共通ですが、販売データを登録したあとは、自分で積極的に宣伝していってください。
無名のアマチュアのペンネームを、検索して来てくれる人はほぼいないと思ったほうがいいです。
SNSのプロフ欄に、販売サイトへのリンクを貼っておいたり、投稿の固定記事にリンクを入れておいたりするのもいいかと思います。
下の記事はイラスト向けですが、テキストの販売も同じような流れです。
選択肢C:プロになった時のためのストックとして寝かせておく
友人知人がwebに作品を公開しているからと言って、焦って無理にweb公開や販売をする必要はありません。
ここぞという時まで寝かせておくという手もあります。
- パクられる可能性はほぼ皆無
- ひょっとすると一生、お蔵入りかもしれない
世に出せば、その作品に対する反応や感想をもらえたりして、作品をブラッシュアップできる、というメリットはあります。承認欲求もある程度満たされるかもしれません。
ただし「公開する=パクられる可能性が生じる」というデメリットは必ずついて回ります。
こんな場末のブログですら、記事ネタをちょいちょいゆるパクなさる企業メディア雇われのライターもいるくらいです。せめて引用という形で使って欲しいなと思いますがむずかしいでしょうか関係各位。
そういうわけで、
「これは誰にもパクられたくない、とっておきのアイデアや思い入れが詰まった作品だ」
と思うのであれば、プロになった時に使うネタとして、温存しておくのも一つの手です。
温存しておくデメリットとしては、プロを取り巻く環境もシビアであり、好き勝手に創作させてもらえるものでもないという点があります。温存しておいたネタが使えるかどうかは、何とも言えないところです。
また、作品やネタはどうしても経年によって古くなります。
10年前に作った作品をそのまま使おうと思っても、なんだかズレている、と思うことも多いのではないでしょうか。
作品の旬を見極めて、使いどころを考えてみることも重要です。
落選作を公開する注意点
同人誌やwebで発表してしまうと、その時点で、その作品の応募権限がなくなる公募が少なからずあります。
イラストはだいぶこの傾向が強いです。また文芸だと、お堅い系(一般文芸など)の小説賞でこの規約を課しているところが多いです。
そういう、「未発表作品のみ受け付けの公募」のうち、応募してみたい公募がもう存在しないかどうか、まず確かめてみてください。
もう公募先が見つからないな、と思ったら、webに載せたり、同人誌(ZINE)などにして販売してみる、という方向で考えてみるのが、公募落選作供養の方向性として、後悔が少ないかと思います。
まとめ
落選作は公募に使いまわす、イベント売りする、ポートフォリオに使う、寝かせておいてここぞという時に使う、など、いろいろ生かす方法があります。
せっかく限りある人生を割いて生み出したものなので、後悔のないように使っていきましょう。
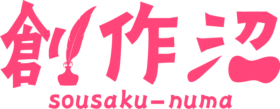
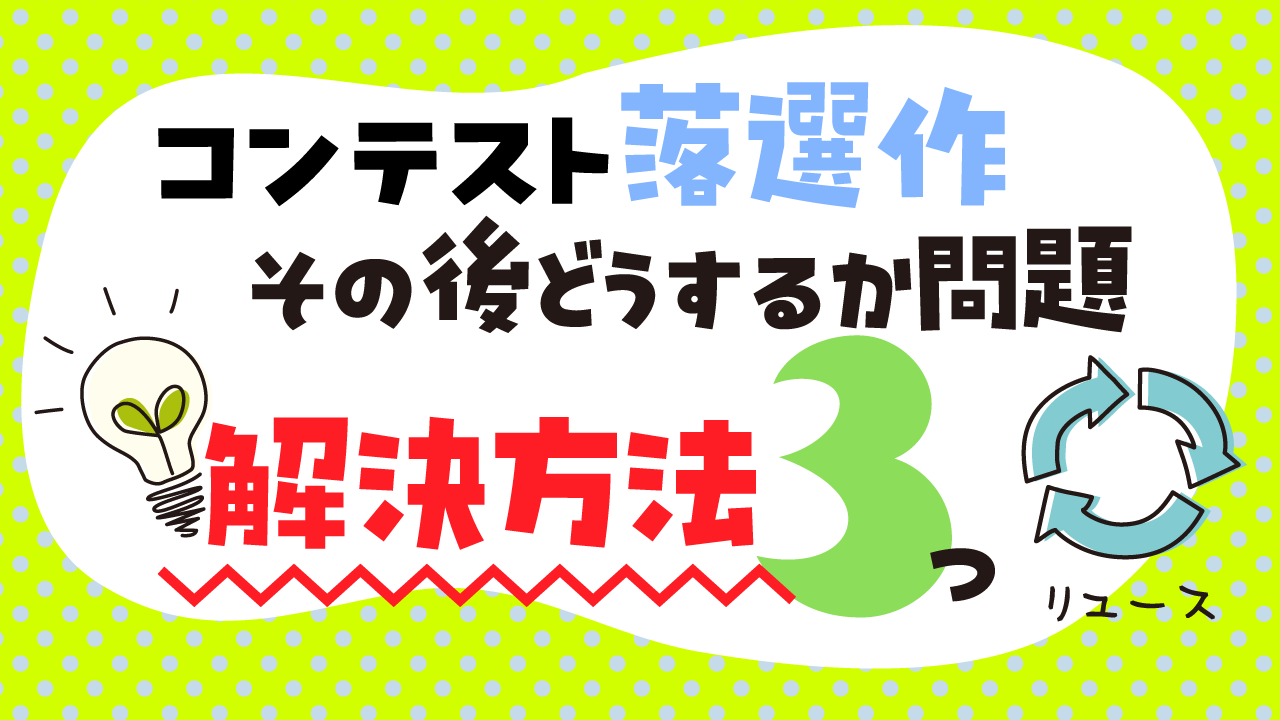

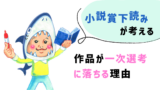
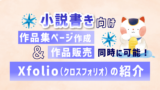
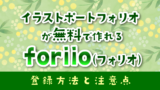

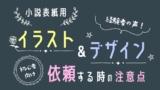
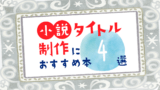
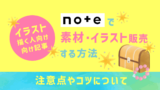
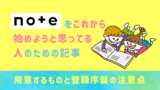
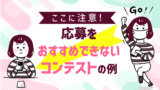
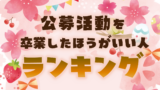
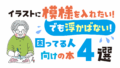
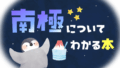
コメント