- なんで小説賞が取れないんだろう、けっこう身内での評価は高いのに、と感じる人
- 身内だけじゃない読者をもっと増やしたい人

web小説投稿を始めたばかりだと、わからないことが多くて、不安もありますよね。
このシリーズでは、数年前までweb小説初心者だった著者が、こんなことでつまづいたので、気を付けたらいいかも、という内容を、小説投稿サイト初心者向けに書いています。
今回の小説投稿サイトビギナー生存戦略は、
の2つです。
以下、どういうことなのか理由を書いていきます。
身内の称賛には感謝しつつも冷静でいよう
Webで小説を上げていると、しぜんと、気の合うユーザーさんと交流するようになってきますよね。
自分の作品を褒めてくれる時もあります。嬉しいですよね。

これ書いてる人も、ノー人脈から小説投稿サイトにアカウントを取ってみて、交流ユーザーさんたちのやさしさに、何度心励まされたか知れません。
それだけに、ここで注意したいことがあります。
Webで交流している友達(=身内)は、基本的に、あなたの作品に対して、良いことしか書かない。
と、思っておいた方がいい。
ということです。
ちょっと考えても見てください。あなたと友達でいたいのに、あえて悪く書いて揉めたいわけがありません。
投稿仲間は良いところを褒めてくれますし、こちらだって言葉を尽くして褒めます。
そこにいいとか悪いとかはなくて、人間関係ってそういう部分があるという話です。
身内による賞賛に浸かっているのは、とても心地が良いです。
しかし、新規読者を増やしたいと考える場合、客観性を忘れてしまうのは危険です。
自分の小説がどのくらいのレベルにあるのかは、冷静に把握しておいたほうがいい
実力を把握できてきないと引き起こしてしまいがちなあるある
自分の実力を正確に把握することは難しいです。
人は主観でしか生きられないからです。
でも、ある程度自分のレベル感がわかっていたほうが、以下のような事態を避けやすいです。
なお、受賞作より私の作品のほうがいいのに、などと思うことは、普通に公募勢あるあるなので安心してください。みんな口に出さないだけです。
自分の実力を客観的に知る方法3つ
人は主観でしか生きられないので、この世に完全に客観視する方法はないです。
ただ、以下の方法を試すと、自分の実力を客観視しやすくなります。
可能ならば以下の3つとも、試してみて欲しいです。
- 小説投稿サイト内のランキングや評価数を冷静に受け止める
- コンテストに参加する
- 身内でない人に作品を見てもらう
小説投稿サイト内のランキングや評価数を冷静に受け止める
小説投稿サイトの多くには、ランキングや評価機能があります。
そこで出た結果から、自分の作品を客観視してみる方法です。
とりあえず向いていそうなサイト2、3個に登録してみて、何か作品を投稿してみてください。
なお、そのアカウントで初めに投稿する時には、長編はやめたほうがいいです。
短編か、できたら中編くらいがいいかなと思います。
小説投稿サイトでのランキングや評価を見てみることで、その作品が、「web小説として人気があるかどうか」が多少わかると思います。
ただ、ちょっと小説サイトを使ってみた人なら感じることだと思うんですが、ランキングは、必ずしも面白さと比例しません。
上位の作品でも、全然面白くなかったり、首をかしげるような内容だったりすることもあります。
ランキングって、いろいろな方法で結構操作できてしまいますし、小説サイトごとの読者の傾向も違うので、あんまり結果を真に受けすぎるのも考え物です。
あくまで参考程度にしたほうがいいです。
また、web小説で受ける作品と、出版社開催のクラシックな公募で評価される作品はまた違ったりするというか、ほぼ別物なので、ランキングが伸び悩んだから駄作、とは考えないほうがいいです。
- ある程度、自分の作品が(そのサイトに来る)読者受けしやすいかどうかわかる
- ランキング不正は日常茶飯事。あまり結果を真に受けないほうがいい
- web投稿に向いた内容の作品と、そうでない作品がある
- そのため、ランキングや評価が伸び悩む作品が駄作とは限らない
コンテストに参加する
コンテスト(公募)に参加してみましょう。
そこそこおすすめの客観視の方法です。
各小説投稿サイトや出版社では、頻繁にコンテストを行っているので、それに作品を投げてみましょう。
なお実力を知りたい場合、選考途中で読者投票がある、SNSフォロワー数や宣伝力がものをいうコンテストは外したほうがいいです。
おすすめは、講評をくれる賞か、短編のコンテストです。
講評がもらえると、どこがダメだったのか把握しやすいです。
また、短編なら制作時間もさほどかかりませんし、コンテスト開催数も長編より多い気がします。

ボツったら使いまわせばいいので、気軽に応募してみては。コンテストは、受賞者より落ちる人のほうが圧倒的に多いので、別に落ちても恥ではないです
おすすめのコンテスト(短編)
超・妄想コンテスト
小説投稿サイト・エブリスタが2週に1回のペースで新しいお題を出している、短編のコンテストです。
この賞は、読者投票がありません。
また、本棚数やスター数が振るわなくても、選考に(恐らく)影響がない賞です。
規定文字数は8000字まで。
賞金枠は3つあり、大賞に入ると3万円が貰えます。さらに、賞に入ると、河出書房新社の『5分シリーズ』というYA書籍に掲載されるチャンスもあります。
(オレンジ文庫の)短編小説新人賞
オレンジ文庫の短編小説新人賞の規定文字数も、妄想コンテストと近いです。
個人出版社の文学賞も狙い目
最近は、ひとり出版社が賞を開催していることも多いです。
ひとり出版社の賞は、受賞して書籍化したとしても流通量が少ない点や、賞の認知度が低い点は、デメリットとしてあります。
ただ、大手の出版社のコンテストと違うよい点は、運営者が、小説が好きで、自分でもコンテストにしたことがある人が多い点です。
そのため、書き手のことを考えた賞運営をしてくれるケースが結構多いです。
たとえば匿名選考をしてくれたり、講評が手厚かったりします。
- コンテストに受賞すると、その作品に興味を持ってもらえるので、読みに来てくれる人も増える傾向にある
- 賞によっては賞金が入ったり書籍化も
- 受賞をSNSでつぶやくとフォロワーが増えやすい
- 受賞は運や出版社との相性もある。真面目に取り組みすぎると心を病みますほどほどに
- コンテストが実力順に受賞させるものだ、と過度に信じすぎないほうがいいです。その開催者にとって欲しいと感じた作品が受賞するのであり、運要素は小さくないです
身内でない人に作品を見てもらう
創作上の友達に見てもらうのは、気楽でいいかもしれません。
ただ、たまには全く知らない人に作品を読んでもらうことで、新しい刺激を受けることもできます。
「いやそういうの、やったことないし……」
という人もいると思います。
どういう方法で第三者に申し込んでいいのかわからない。どういう人に読んでもらうといいかわからない。
そういう人向けに、個人的おすすめを、この記事に書いてみました↓
まとめ
- 小説を褒められた時こそ冷静に
- 短編コンテストは、実力チェックになるので、参加がおすすめ

次の記事は、「相手の小説の感想を書くことによって、自分の作品を読んでもらいやすくなる。じゃあ、その書き方のコツとは?」という内容です↓
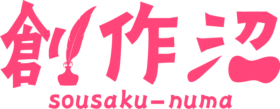
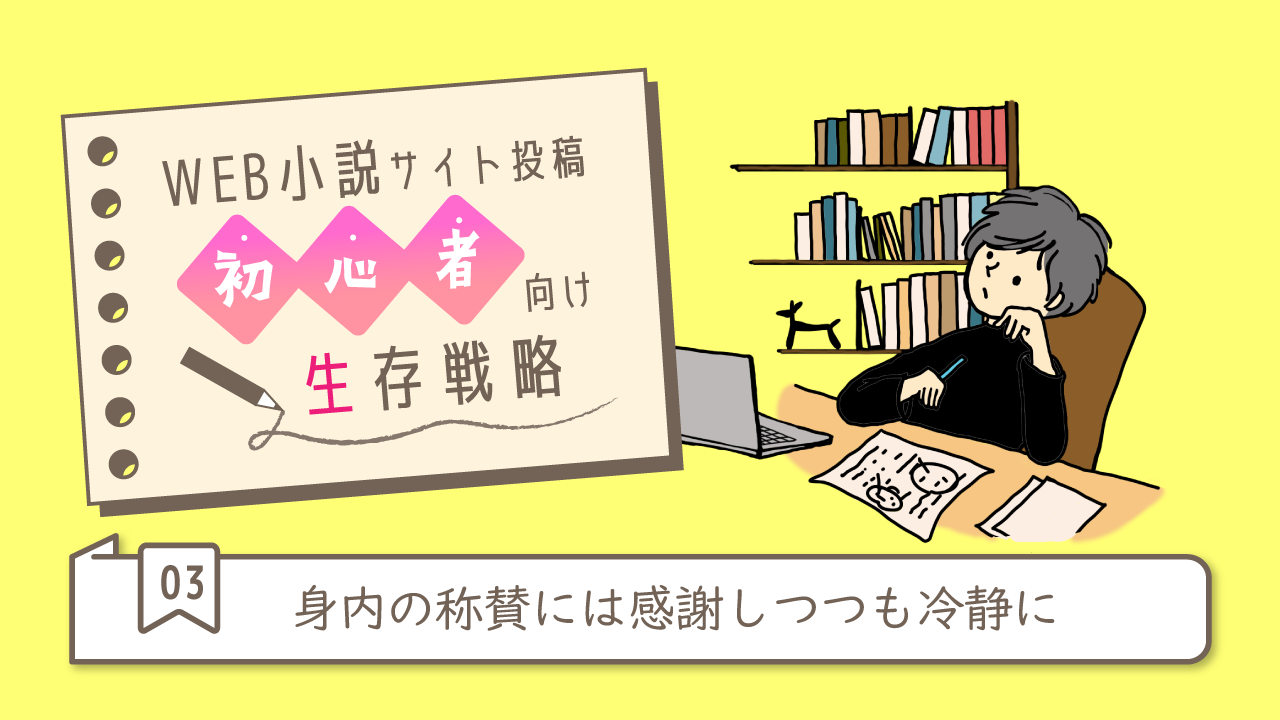

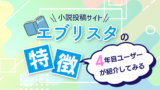
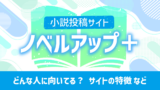

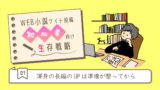
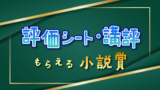
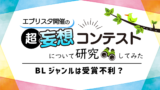

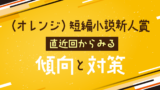
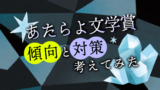

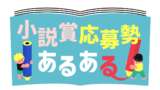
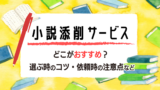

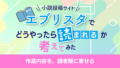
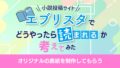
コメント